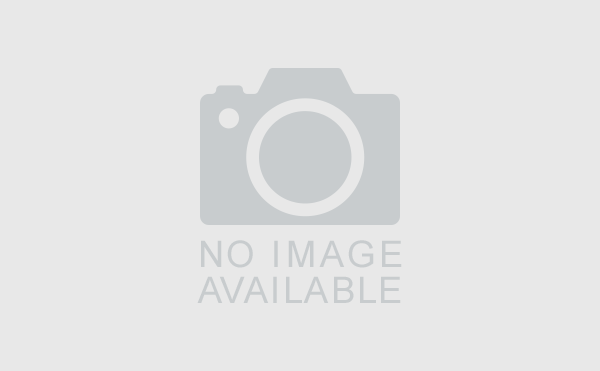皆さまいかがお過ごしでしょうか。
秋田高専のホームページにようこそ。
秋田高専の校長の高橋です。
今年は大雪のニュースが多いです。
2月に入っても雪は続いていますが、広い秋田県では地域によって雪の降り方に差があります。
秋田高専のある秋田市は、海に面しているからでしょうか、風は強いですが内陸の地域のような何メートルという積雪にはなっておりません。道路は市役所が除雪をしてくれるので、道の両脇に雪が寄せられて道幅が狭くなったり見通しがきかなくなったりはしますが、運転手のみなさんが譲り合いの精神を発揮してスピードを控えめにして走るので、なんとか通行できる状態になっています。
雪下ろしが必要になる内陸部の豪雪地帯の苦労を思えば、秋田高専で雪がどうのいっている場合ではない、ということでしょうか。
秋田県の気候について申し上げましたが、県内各地で進められている風力発電も、天候の影響を強く受けます。
現在、風力発電の風車は沿岸部に多く建設されていますが、これは日本海からの強い風を風車に受けるためには、ひらけた沿岸部が適地となるからです。今後は、洋上にも風車の設置を進めていくことになっています。
秋田高専では、秋田県をあげて進められている風力発電の事業を、学生を教育するためのこれ以上ない教材であるととらえています。
秋田高専の目指すのは、社会で活躍できる技術者=エンジニアです。このためには、社会の様々な活動に学生が直接触れること、関係している方々から直接話を聞くことなど、学生が実際に体験して刺激を受けることが必要です。殊に地元秋田のホットな話題である風力発電は、実践的な学びのためのうってつけの教材となります。
2月25日、春休み中だったので参加できたのは限られた学生でしたが、常々秋田高専を支援してくださっている大森建設のご厚意で、能代市の風力発電のサイト「風の松原風力発電所」を見学する機会をもつことができました。
まず、秋田高専のOBであり、大森建設で風力発電の関係を中心となって進めている石井さんから、風力発電所を立ち上げるための準備の段階から現在までの一連の流れをご説明いただきました。
「風の松原風力発電所」は、全部で17基の風力発電用の風車で構成され、2016年から運転を開始しています。設備投資額は160億円、金融調達額は182億円に達します。投入された資金の大きさからも発電所の規模の大きさがわかります。
これだけの規模の発電所となると、実際に工事に着手する前の段階での準備、つまり様々な関係先との交渉と調整が必要になってきます。金融機関との資金調達のための交渉や東北電力との売電契約関係の交渉。地元関係者の理解を得るための説明会の開催をはじめとした話し合い。環境アセスメント。などなど。
天候に左右される風力発電の弱点を乗り越えるための技術的課題を克服することはもちろんですが、風力発電所の建設は、技術だけでは完成することのできない社会的なプロジェクトです。安全性や社会との調和の観点、ビジネスとして成立し継続していくための経済性の観点などを含めて、全体として考えていくことが求められます。高専の学生はエンジニア志望ですが、技術を社会の中で活かしていくためには、技術の知識だけではでは決して十分ではないことを学ぶことができたのではないでしょうか。風力発電所は、社会に新しい技術が受け入れられ社会に良い変化をもたらす好事例です。社会の中での技術のあり方を学ぶための恰好の教材です。
「風の松原風力発電所」では、風力発電所と社会とをつなぐための工夫も怠りありません。風力発電は、発電量が風力の変化によって変動することが避けられません。そこで、安定的に送電するために、同発電所では大規模な蓄電池をシステムに組み込んでいます。風の強い発電量の大きなときに充電しておいて、風の弱い発電量が十分ではないときには充電池から電気を補充して送電しています。災害で停電が発生した際には、この蓄電池から地域に電力を供給する準備を整えているのです。
大森建設は、現在、能代市の内陸部に新たな風力発電所を計画しています。内陸部となれば、風車の立地などに関して関係者は沿岸部よりもずっと多くなり、土地利用の規制などとの調整は一層骨の折れる仕事となります。内陸部での風力発電所新設に向けて、大森建設は地元の能代市への貢献のためのアイデアに次々トライしています。一つ一つ自力で工夫を重ねて技術的な社会的な課題の克服に努めています。
大森建設の皆様の工夫と努力には頭が下がります。柔軟で豊かな発想には感服するばかりです。
さて、風力発電の風車に関しては、100%が外国からの輸入です。だからといって輸入したものを組み立てて建設すればよいということではありません。風車の部品を運ぶ貨物船がスエズ運河を使えるのか喜望峰周りの航路になるのかで、コストや納期に大きな違いが生まれます。そして、なによりも事業計画に大きく影響してくる天候以上に予測が困難なのが、為替の変動です。
ここまでくると、もう世界情勢に直結してくるグローバルな問題となります。
秋田高専の目指すのはグローバルエンジニアですが、秋田の地元の風力発電所の建設にしても、グローバルな関わりなくしてはなにも進まない。技術に国境なしです。一人前のエンジニアたるためには、グローバルな視野と力量が必要になる現代です。
そこで秋田高専では、エンジニアに求められる社会の要請に応えていくために、教育の現代化を試みています。
とはいえ、中学卒業後の5年間にセットされた高専教育の目指す水準をクリアするためのカリキュラムがありますから、なんでも自由に組み替えられるというものではありません。高専教育の枠組みを活かして、その内容を見直して時代や学生の変化に対応させたものにしていく。
このためには、秋田高専の教育に、ご紹介したような現地での体験や外部の専門家による指導を取り入れていくことが必要です。海外での経験も必要です。そして、高専を卒業してからエンジニアとしてグローバルに仕事をこなすためには、英語力の基礎は身に付けなければなりません。
秋田高専は、教育の現代化を進めるために、今年度から高専機構(独立行政法人国立高等専門学校機構)から特に予算の配分を受けています。学生の海外研修派遣にも、高専機構からの援助をいただいています。
これらも活かしながら、大森建設を始めとしたご支援いただいている皆様の力をお借りして、どこまでのことができるのか、秋田高専の力量が試されています。